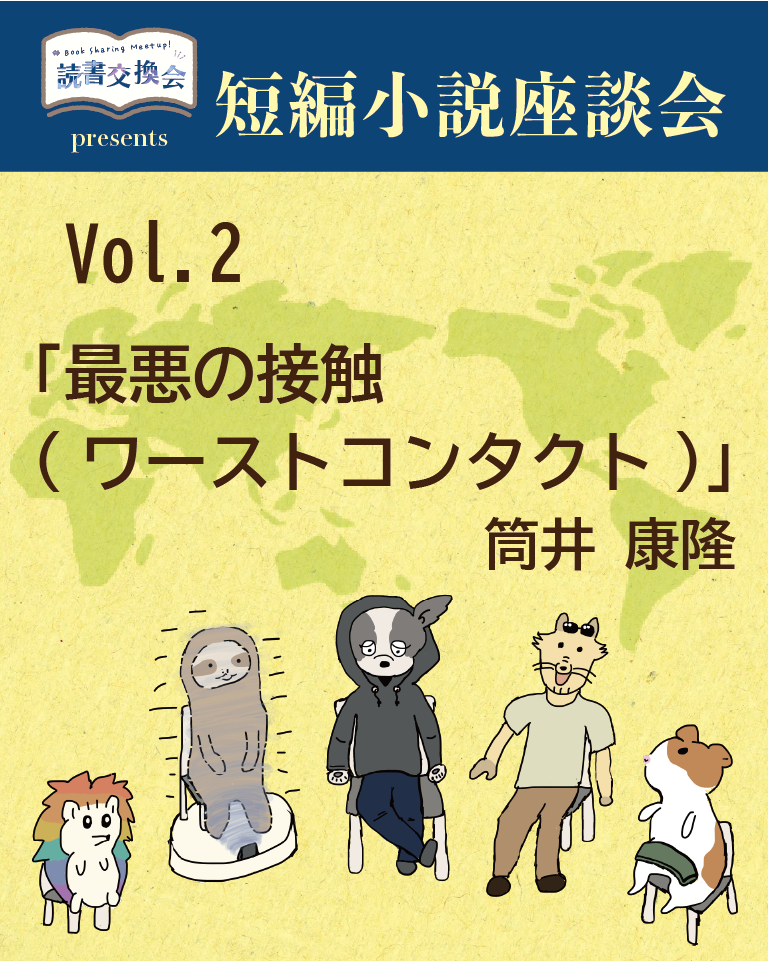
今回から座談会の本題に入っていきます。最初の作品は主催者である僕、いまちゃんが選んだ人生で一番好きな短編小説で、この作品です。
「最悪の接触 (ワーストコンタクト)」 筒井 康隆
あらすじ *ネタバレ有り
マグ・マグ人という異星人との初接触の任務を任された主人公。しかしマグ・マグ人は、挨拶の直後から主人公を殴ったり、以後も支離滅裂な言動を続け、主人公は滞在期間中に錯乱状態に陥る。帰還後、地球政府は主人公の報告を待たずにマグ・マグ人との交流を決定してしまい、マグ・マグ人の支離滅裂な言動によって、地球は混乱に陥る。後に主人公が書いた報告書が出版され、マグ・マグ人の間でベストセラーとなる。その理由は「人間がよく描けていた」からだそうだ。
いまちゃん推薦理由
 いまちゃん
いまちゃん前回の記事で話した、プロットとストーリーの話の続きになるんですけど、物語を作る時に、キャラクターの設定を作り込むと、プロットを立てる時に制約がかかってしまう、っていうジレンマがあるんですよね。「こいつはこういうキャラだから、こんな行動は取らないだろう」みたいな感じで物語の展開を作りづらくなってしまう訳です。
で、この作品の画期的な所は、「キャラクター設定が破綻しているキャラクター」を登場させたところです。
通常はキャラクターの言動には一貫性が必要ですが、マグ・マグ人は完全に破綻しているキャラクターであるため、どんな言動をしても全体としては成立します。その結果、キャラクターの心理(ストーリー)に制限されずに、展開(プロット)を自由に進められるんです。僕はこの作品を今回読み返してみて、こういう“構造から逆算された作品”が好きなんだと、改めて思いました。
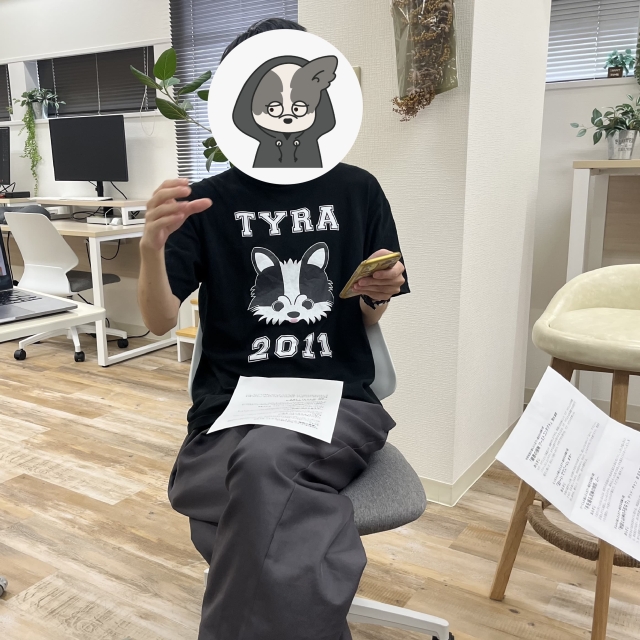
みんなの感想
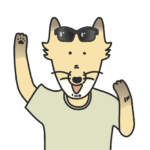 けーくん
けーくん僕は今回、筒井康隆の作品を初めて読んだんですけど、最初読みにくくて仕方なかったんですよね。マグ・マグ人に対して、主人公と同じ気持ちで、「コイツはコイツなりに何かルールがあるんじゃないのか?」とか、勘ぐって読んでいたんですけど、最終的には無かったということで。
確かに構造的な話で言うと、破綻していても成立するような感じになってますけど、僕は、ある種のミステリーみたいに、最後に謎が解明されて、腑に落ちるパターンなのかな?と思って読んでいました。
でも、この話はそうではなかったので、僕としては新しい感性なのかな?って思いました。
 いまちゃん
いまちゃんシュールレアリズム系の不条理な作品とかだと、「夢か?現実か?」みたいな感じで起きてる現象、すなわちプロットの方が訳分からなくなって、最後まで訳わかんないまんま終わる作品は結構多いんですよね。
でも、この作品だとプロットの方は明確に分かっているけど、キャラクターの内面のストーリーの方が分からないっていうのが非常に画期的だなと。キャラクターの内面だけを破綻させてるっていうのが、新しいなって思ったんですね。
 えっちゃん
えっちゃんそこまで考えて読んでなかった。何か単純に、「いまちゃんが好きそうだな」と思って読んでました。
 よーちゃん。
よーちゃん。私は、読んだ時の最初の感想としては、古さを感じないというか、「最近書かれた話でもおかしくないな」って思ったかな。
で、会話が通じないっていうのが、今、インバウンドでいっぱい海外の人が来てるやんか?、その人たちとの文化の違いを最近感じることが多かったから、そこと共通してる部分を感じて、響くものがあったかな。
 いまちゃん
いまちゃんよーちゃん。は「何かのメタファーじゃないか?」と思って読んだんですね。逆に僕は全然そういう読み方をしてなくて、物語の構造ばっかり見てましたね。
 まなみちゃん
まなみちゃん人によるよね、読み方って。
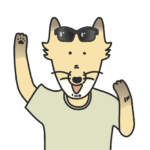 けーくん
けーくんメタファーで言うと、今回読んだ中だと僕は、星新一の「おーい でてこーい」の方が、バリバリの社会派だったかな?と思いました。
 まなみちゃん
まなみちゃん私はそこまでメタファーとか構造とかは全く考えずに、読んだんやけど。
感想としては、けーくんが言ってたように、「どういう理屈でこいつは動いてるんだ?」と理解しようとして読んだんだけど、最終的に、「こいつに理屈も何もないんだよ、ぺしっ!」ってされて、「ああ、、、」みたいな。オチが何か、「地球がめちゃくちゃになったよ!ちゃんちゃん!」みたいな感じで、ほんまに何も理由が無いんや!って思った。
だからこの作品を読んで、「自分は普段から考えすぎなのかな?」と思ったかな。例えば職場に、訳の分からない行動をする今枝(いまちゃん)が居ると、「何でコイツはこんなことをするんだろう?」って思うけど、「そんなのを考えてもしょうがないと思うよ!」「そんなのどうでもいいじゃん!」みたいな風に、私は受け取りました。
 いまちゃん
いまちゃん何か、僕、すごいこと言われましたけど、(苦笑)
 えっちゃん
えっちゃんでも、まなみちゃんのその感想、ポジティブな感じはしますね。
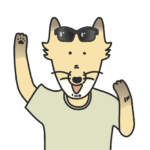 けーくん
けーくんそうね、「人の行動は自分が理解できる」とか、「他人に自分のことをどう理解されているのか?」とか、そう言うのは絶対的なものではない、みたいな事だよね。
 いまちゃん
いまちゃん一応この作品自体、筒井康隆が「不思議の国のアリス」の、3月うさぎっていうキャラクターから影響を受けて書いたらしいんですよね。僕はまだ、「不思議の国のアリス」は読めてないんですけど。
 まなみちゃん
まなみちゃんあー、確かに。理不尽さは、「不思議の国のアリス」感ある。
 いまちゃん
いまちゃんホラー映画の連続殺人鬼とかだと、「キャラクターが連続殺人をする動機が、最後までよくわかんない」みたいな映画とか、いっぱいあるんですけど、それに近いなとも思いますね。
筒井康隆の他の短編で「走る取的」っていう、「ひたすら相撲取りに追いかけられるけど、相撲取りが追いかけてくる理由は、最後までよく分からない」みたいな内容のホラー小説があるんですよね。その作品に影響を受けて黒沢清監督とかが映画を作って、更にそれに影響を受けてパラサイトのポン・ジュノ監督も映画を作ったりしてるんですよね。
だから後に世界的に展開される、「最後までキャラクターの行動原理がよくわからない」っていうジャンルの作品を、50年も前にやったのが筒井康隆だったのかな?と僕は思いましたね。
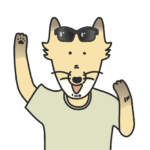 けーくん
けーくん何か理解できない物が一番怖い、みたいなのあるよね。
 えっちゃん
えっちゃん私も割と、まなみちゃんと似た感じで、ポジティブに読みましたね。支離滅裂だなとは思ったんですけど、別にイライラまではしなかったです。
でも、「地球がグチャグチャになりました、ちゃんちゃん!」ってオチは、ちょっと嫌やったな、って思いました。キャラクターに理屈が欲しいというよりも、「人間じゃない物と、分かり合うことができない」みたいなオチが嫌でしたね。でも筒井康隆は、そんなメッセージを込めて作ってないんだろうな、とも思いましたけどね。
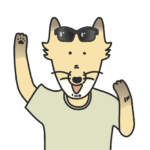 けーくん
けーくん僕はオチは、「地球が大変なことになった」っていう所ではなくて、「彼の報告書が単行本となり、最終的に向こうの星のベストセラーになった」っていう所なのかな?って思いましたね。
地球が大変なことになってる所は、何か結果だけが書かれている感じがして、もうちょっとインパクトあってもいいかな?とも思ったんですけど、最後の「人間がよく描けていた」って言うところは、クスッと来て好きでしたね。
主人公とマグ・マグ人がお互いの視点で、全然違う所を見てたよね、っていうのを、さらっと一言で表したのが、あのオチなのかな?と思いました。
 よーちゃん。
よーちゃん。でも何か私は、いまちゃんは、もうちょっと難しい哲学的な作品を持ってくるかな?と思ってた。
 いまちゃん
いまちゃんえ、この作品も、ある程度哲学的じゃないですかね?
僕この作品の、成立してない台詞とか、文章として成立してない文章みたいなのが凄く好きなんですけど、そういう所が言語哲学的だな、と思いますけどね。
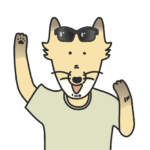 けーくん
けーくん僕はその、文章が成立してないところが、凄く読みにくかったんだけどね(笑)
構造で読んだり、メタファーとして読んだり、みんな色んな読み方をしていて、とても興味深かったです。残りの4作品もこんな感じでやって行きます。次回は、えっちゃん推薦の星 新一「おーい でてこーい」です。
