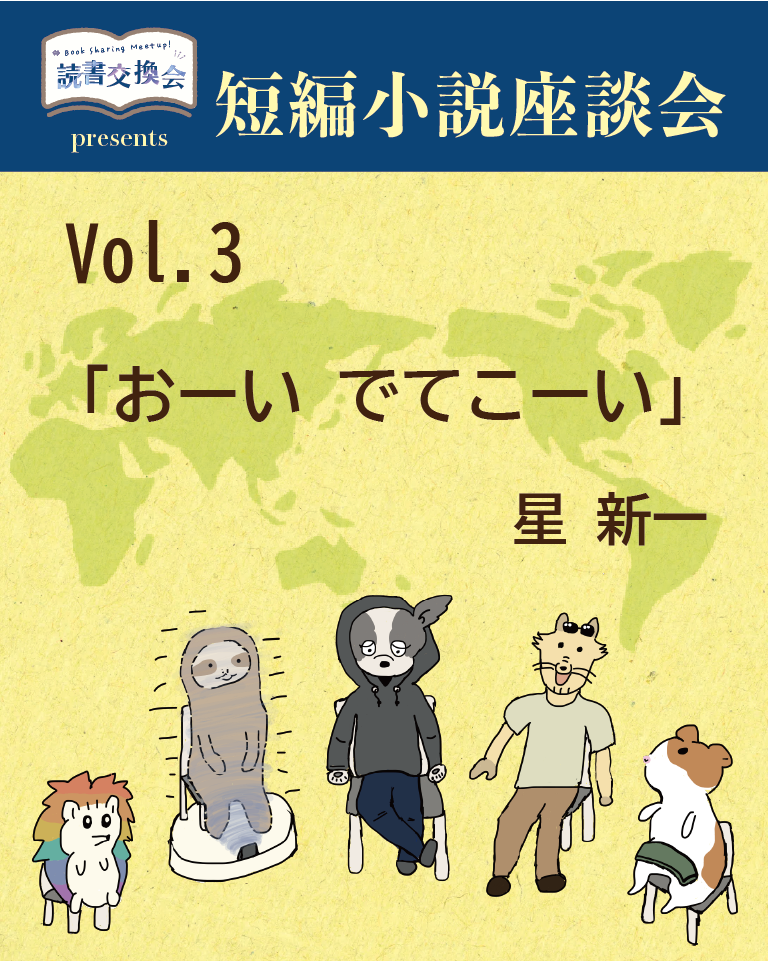
今回は、えっちゃんが推薦した作品について語り合います。
この作品は文庫本でわずか9ページという、今回取り上げた5作品の中では、最も短い作品です。それにもかかわらず、読者に強烈な印象を与えることから、発売から半世紀経った今でも根強い人気です。
有名な作品なので、あらすじを知っている人も多いかもしれませんが、まずはあらすじから、どうぞ。
「おーい でてこーい」 星 新一
あらすじ *ネタバレ有り
台風が過ぎ去った後、地面に大きな穴が出来ていた。試しに穴に向かって「おーい でてこーい」と叫び、石を落としてみるも、何の反応もない。やがて、人々はその穴にゴミを捨てたりと、有効活用し始める。最終的にその穴は、産業廃棄物の集積場所として人々から重宝されるようになる。そんなある日、男が座っていると、どこからか「おーい でてこーい」という声が聞こえてきた。そのすぐ後に、上から石が落ちてきた。
えっちゃん推薦理由
 えっちゃん
えっちゃん私は、考えさせられる作品が好きです。特に正義を題材にした作品で、ちょっと説教されるような要素があると、むしろ嬉しくなります。
今でこそ「正義の暴走」とか「正義の反対は正義」とか、いろんなレトリックがあって、「正義は相対的だ」と言われることも多いですよね。でも、私はやっぱり「正しくて良いこともあるじゃないか?」と思うんです。
世の中には、絶対的な正義もあると思っていて、むしろ、「正義は相対的だ」と語るタイプの作品のほうが、かえって説教臭く感じることが多いです。
「おーい でてこーい」は、環境問題みたいなテーマを考えるのが苦手な人には、少し取っつきにくいかもしれません。でも私にとっては、星新一の作品を読むと、心地のいい説教を受けたような気分になるんです。
だから今回は、星新一作品の中から推薦する作品を選ぼうと思ってて、その中で一番に浮かんだのが「おーい でてこーい」でした。

みんなの感想
 いまちゃん
いまちゃんこの作品って、最短でフリとオチを繋いだ、すごくコンパクトな話だと思うんですよね。作品内に、キャラクター名とかも一切出てこないじゃないですか。それに比べると、まなみちゃんの選んだ「地獄とは神の不在なり」とかは、「正直、この役はキャラクター名無くてもよくない?」みたいな脇役にも、フルネームが付いてたりしました。
だから僕はこの作品を読んだ時、「えっちゃんは、作品のディテールより構造に惹かれるタイプなのかな?」と勝手に思ってました。でも実際は、「構造の上にある社会派的なテーマがいい」という感じなんですね。
 まなみちゃん
まなみちゃんいまちゃんは、やっぱり構造が気になんねんな(笑)
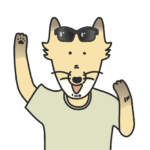 けーくん
けーくん僕は、この作品を読んで、「えっちゃんっぽいな」って思いました。
僕も、星新一は結構読んだことがある作品も多いんですけど、えっちゃんは以前の読書交換会で、ミステリー小説とかじゃなくて、ビジネス本とか、そういう社会派的なやつを選んでたんで、このテーマの作品を読んだ時に、「あ、なるほどね」と思いました。
ホラー感もありつつ、ループしてる感じがSF感もありつつ。その上で、誰かのツケを誰かが払って、みたいなテーマもあって、そこら辺が星新一感があるなと思いました。
 いまちゃん
いまちゃんまなみちゃん推薦の「地獄とは神の不在なり」の作者、テッド・チャンが書いた、「バビロンの塔」って作品が「おーい でてこーい」に似てるって、まなみちゃんに言われたんですよね。で、「地獄とは神の不在なり」と同じ短編集に入ってたんで、読んでみたら、大筋は似てたんですけど、「バビロンの塔」の方が「おーい でてこーい」に比べると、だいぶ細かいディテールまで詰められてましたね。
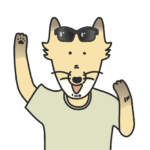 けーくん
けーくんまあ星新一と比べたら、長さがだいぶ違うだろうからね。
 まなみちゃん
まなみちゃんテッド・チャンの「バビロンの塔」ってどんな話かって言うと、
–ここからテッド・チャン「バビロンの塔」のネタバレ–
バビロンの塔っていう世界一高い塔を建ててるんよね。世界中から工事のために人が集まって来て、塔の周りは大きな町になってて、どんどん塔は上に上に高くなって行くんよね。
で、その世界には天井があるんやけど、岩で出来た天井に到達するんよ。でも、その天井を叩き割って、更に上へ上へと進んでいくんよね。
そうやって岩を掘りながら上に進んでいくと、最終的に、まあ色々あって、地球の地底から出て来ましたっていうオチで。「おーい でてこーい」の逆バージョンというか、上方向に行った時の話。
—テッド・チャン「バビロンの塔」のネタバレ終わり–
だから、ちょっと話が似てて、「おーい でてこーい」を読んでて、びっくりしたかな。
 えっちゃん
えっちゃんざっくり聞くだけでも「私、その話、好きやな」って思いますね。
 まなみちゃん
まなみちゃんでも私の感想としては、けーくんと違って、「えっちゃん、これを薦めるんや!」って、ちょっと意外やったかな。社会派的な思想よりも、すごい簡潔な構成の作品を選んできたって所が、すごい意外だったかな。何か、「割って、パカ!」みたいな、 「起!結!」みたいな。
えっちゃんは、そういう裏表のない、勧善懲悪的な世界観が好きなんやって、新たな一面が分かったから、読んでて面白かったかな。
 いまちゃん
いまちゃんあと、この作品って、タイムトラベル的な要素もあるわけじゃないですか。また構造の話になって恐縮ですけど、タイムトラベルとか、時間軸を動かす系の作品って、伏線回収が作りやすいんですよね。
この作品だと、「穴に向かって叫んで、石を落とす」っていう原因を見せた後に、普通の時間軸よりも遅らせて、「叫んだ声が聞こえてきて、上から石が落ちて来る」っていう結果を見せることで、その間に物語を作ってる訳です。
だから、「タイムトラベル系の作品って、原因と結果を見せる位置を、自由に調整できるから、伏線回収がいっぱい作れて、プロット的に面白くしやすいよね?」っていう傾向があると思うんですけど、この作品は、それを最短で実現してるのが、すごいなと思いましたね。
 えっちゃん
えっちゃんすごいな、その感想は。自分では思いつかへん。
 よーちゃん。
よーちゃん。私は、この作品を読んで、暗くもなくて、考えさせられる内容が、すごい、「えっちゃんっぽいな」って思ったかな。
「こんなところで、最後つながるんや!」みたいなオチに、「自分の身から出た錆は、自分に返ってくる」みたいなメッセージを感じたんよね。
だから今、私たちが捨ててる物も、未来の人の身に降って来るなら、ちょっと考えていかなあかんな、って思ったかな。
私は割と、作品のテーマに共感する、みたいな読み方をする事が多くて、特に今回読んだ5つの短編は、考えさせられる作品が多かったかな。
 いまちゃん
いまちゃん僕は、「作品を見たことで、何かを考えさせられる」っていう経験が、人生でほぼないんですよね。だから、よーちゃん。は、本当に僕と全然違う読み方をしてるんだな、って思いました。
まなみちゃんとか、よーちゃん。は、二人が今回選んだ作品の傾向からも、プロットとか構造じゃなくて、「細部への共感」とかで読んでるんだろうなって思いましたね。
よーちゃん。や、まなみちゃんは、プロットで読まないからこそ、太宰とかテッドチャンみたいな、ディティールや描写に凝った作品を挙げてきてるんだろうなと。だからこそ二人は、筒井康隆とか星新一みたいなプロットから作られているような作品を読んでも、共感とかディティールについての感想を語るんだろうなと思いました。
逆に僕はプロット人間なんで、すごい共感するはずの純文学とかを読んでも、その物語の構造の話ばっかりするんだろうな、って思いましたね。
 えっちゃん
えっちゃんいまちゃんみたいに、「考えさせられるっていう事がない」っていう人もおるんやね。私と読み方、全然ちゃいますね。
でも確かに言われてみたら、星新一の作品って、構造も優れてる作品が多いなって思いました。そう考えると私も、無意識に構造にも惹かれてたんかも?って思いましたね。
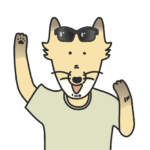 けーくん
けーくんいまちゃんが「共感しない」っていうのは、そういう風な読み方をして来なかっただけかもしれないけどね。
 いまちゃん
いまちゃん「はじめに」で言った、今回の5つの作品の傾向の話にも戻るんですけど、筒井康隆、星新一、乙一の上の三つの作品は、全体の構造から作品を作り始めてると思うんです。一方で、下のテッドチャンと太宰治の2つの作品は、テーマとかディティールから話を作ってると思うんですよね。
だからやっぱり僕は、この作品を読んで気になったのは、どのタイミングで作品のテーマである「環境問題」と、「未来と繋がっている穴」という設定をくっつけたのかな?っていう所ですかね。
僕の予想としては、穴の設定を先に思いついて、それを後から環境問題に紐付けて作品を作ったのかな?って思ったんですよね。というのも、プロットを先に考えてから作らないと、こんなに綺麗に話が纏まらないと思うし。仮に、「環境問題についての話を作ろう!」って考え始めたとしたら、「穴」の発想に行きつかないだろうな、と。
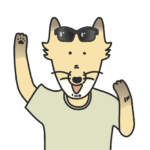 けーくん
けーくん確かに、穴が未来と繋がってたら面白いだろうな、ってところからスタートしてる感はあるよね。
 いまちゃん
いまちゃんだから、この作品はプロットから立てて、後から上手くその上にテーマ乗せた気がするんですよね。でも、よーちゃん。とか、えっちゃんは、そういう作品でもプロットじゃなくてテーマの方を見てるんだっていうのは、思いましたね。
 よーちゃん。
よーちゃん。だから私は、短編が苦手なんは、そこなんよね。読んでてテーマに共感して、自分の気持ちが乗って来たところで、話が終わっちゃうから、「今からじゃないの?」って思っちゃう。「美しい情景とか描写を、もっと膨らませてよ!」って思っちゃうんよね。
 まなみちゃん
まなみちゃん私は短編読むのも好きやけど、どっちかって言うと、よーちゃん。と同じかな。「もっと膨らませてよ」って思う派かもね。
いかがでしたでしょうか。僕が色々と喋ったせいでもありますが、作品の短さの割に、記事自体は長くなってしまいましたね。個人的にはVol.3にもなると、みんなの感想の傾向が割とはっきりと分かれて見えて来たと思います。
次回は、けーくん推薦の「手を握る泥棒の物語」について、みんなで語り合います。
